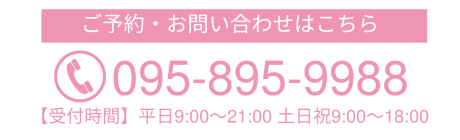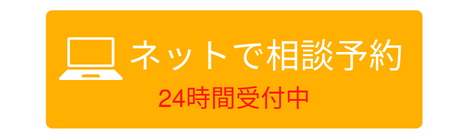Q&A

Q&A
不倫相手が裁判を無視!慰謝料は請求額どおりもらえる?擬制自白と慰謝料額の裁判所判断を弁護士が解説
Question
配偶者の不倫が発覚し、不倫相手に慰謝料を請求しましたが、相手は無視し続けました。
そのため、不倫相手に対して慰謝料請求訴訟を起こしました。
しかし、相手は答弁書も提出せず、裁判にも出てこなかったため、「擬制自白(ぎせいじはく)」が成立して裁判が終わりました。
この場合、私が請求した慰謝料の金額もそのまま認められるのでしょうか?

Answer
「いつ、誰が、誰と不貞行為を行ったか」など慰謝料算定の基礎となる「事実」には自白が成立します。
一方、慰謝料の「金額」については、話が異なります。
たとえ相手方が金額について具体的に争わなくても、擬制自白によって自動的に請求額どおりに決まるわけではありません。
裁判所が自白が成立した事実をもとに相当な金額を法的に判断します。
そのため、擬制自白が成立したからといって、必ずしもご相談者様の請求額どおりの慰謝料が認められるわけではないのです。
この記事では、この「擬制自白」と不貞慰謝料の金額がどのように決まるのかについて、分かりやすく解説します。
1 「擬制自白」とは?~裁判で相手が反論しないとどうなる?~
1.1 擬制自白とは?
「擬制自白」とは、裁判の中で相手方の主張した事実争うことを明らかにしない場合に、その事実を自白したものとみなされることをいいます(民事訴訟法159条1項)。
裁判を起こされた被告が、裁判の期日に出頭せず、原告の主張する事実を争う旨を記載した答弁書の提出もしない場合には擬制自白が成立します(民事訴訟法159条3項)。
民事訴訟法159条
1 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
1.2 擬制自白の効果~争わない事実は認めたことに~
自白が成立した事実については証明する必要がなく(民事訴訟法179条)、裁判所は自白が成立した事実をそのまま判決の基礎としなければならないため、自白の成否は裁判の結論に大きく影響します。
簡単に言えば、相手の言い分に対してきちんと反論しなければ、その言い分を認めたことになってしまう可能性があるということです。
民事訴訟法179条
裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
2 「自白」の対象になるもの、ならないもの
2.1 自白の対象は具体的な「事実」のみ
重要なのは、自白の対象となるのは、あくまで「事実」(民事訴訟法159条、179条)であるという点です。
例えば、「配偶者がAさんとホテルで不貞行為を行った」というような具体的な出来事が「事実」にあたります。
2.2 「法的評価」は自白の対象外
一方で、その事実から法的にどう評価されるかといった「法的評価」は、自白の対象にはなりません。
では、不貞行為の「慰謝料額」は、この「事実」と「法的評価」のどちらに近いのでしょうか?
もし慰謝料額が単純な「事実」として扱われるなら、相手方が争わなければ請求額どおり認められることになりそうです。
しかし、もしそれが「法的評価」を含むものだとすれば、不倫の具体的な行為(いつ、誰とどこで、など)は自白によって認められたとしても、金額については裁判所が別途判断することになります。
この点について、裁判所は、慰謝料額を単純な「事実」ではなく、「法的評価」を含むものとして捉える傾向にあります。
そのため、慰謝料額そのものについてまで、擬制自白の効力が自動的に及ぶわけではないと考えられています。
次の章で、この考え方を裏付ける実際の裁判例を検討します。
擬制自白と自白の対象については、詳しくは以下の記事をご覧ください。
関連記事:【放置は危険!】擬制自白とは?裁判で不利にならないための基礎知識を弁護士が解説
3 裁判例の検討
3.1 裁判例
過去の裁判例を見てみると、慰謝料額そのものは自白の対象外とされる傾向がありますが、裁判所は主に以下のような理由を述べています。
・理由1:慰謝料額等の損害の評価は自白の対象外である
慰謝料の金額は、精神的苦痛など「損害がいくらか」という評価そのものです。
裁判所は、このような評価について、たとえ当事者が特定の金額を認めた(あるいは争わなかった)としても、それに機械的に従うのではなく、提出された証拠や様々な状況を客観的に見て、最終的に判断すべきであると考えています(裁判例②参照)。
・理由2:慰謝料額の算定については裁判所の裁量に委ねられている。
「いつ、誰が不貞行為をしたか」といった具体的な「事実」は、当事者が争わなければ認められます。
しかし、それらの事実から「このケースの慰謝料はいくらが妥当か」を最終的に決定する作業は、多くの事情を総合的に考慮する裁判所の専門的な「裁量(判断の余地)」に委ねられているとされています(裁判例③参照)。
・理由3:法規の要件を充足するか否かの法的判断や慰謝料額等の算定については自白の拘束力が働かない。
法律をどのように解釈し、認められた事実から法的にどのような結論(例えば慰謝料額をいくらにするかなど)を導き出すか、といった専門的な法的判断については、当事者が何かを主張したり認めたりしたとしても、裁判所がそれに縛られるものではない、と解されています(裁判例④参照)。
・理由4:慰謝料額については「弁論主義」の適用はない。
民事裁判では、裁判の基礎となる訴訟資料の収集は当事者の機能かつ責任とされています(これを弁論主義といいます。最高裁昭和59年9月20日第一小法廷判決・税資139号596頁参照)。
自白は弁論主義の一内容ですが、慰謝料の金額をいくらにするかという点については弁論主義の適用がないため、裁判所は当事者の主張額に縛られずに裁判所が適切な金額を認定できる(裁判例⑤参照)。
これらの裁判例は、裁判所は慰謝料額を単純な「事実」としてではなく、法的な評価や専門的な裁量を含むものとして扱い、自白の対象としないとの判断を示しています。
では、この一般的な考え方は、「不貞行為の慰謝料」についても同じように当てはまるのでしょうか。次のセクションで詳しく検討します。
「慰謝料額は自白の対象となる事実ではないから,裁判所を拘束するものではないし,前記過失相殺に係る被控訴人の主張によれば,被控訴人が慰謝料額を争っていないともいえない。」
「なお,そもそも慰謝料額等の損害の評価については,自白の対象外というべきであるから,裁判所としての認定が必要になるはずであるが,原審においてこの点を意識した形跡はない。」
「慰謝料算定の基礎となる事実については右のとおり擬制自白が成立するが、右基礎事実を前提とする慰謝料額の算定については当裁判所の裁量に委ねられているので、慰謝料額について、以下具体的に検討する。」
「なお,以下に述べるところは,原告の各請求に係る法規の解釈及び請求原因事実を前提にして当該法規の要件を充足するか否かの法的判断や慰謝料額等の算定であって,これらについては先に述べた自白の拘束力は働かないものと解される。」
「上記擬制自白のほか,本件事故により生じた原告X2の傷害の内容,程度,通院期間に加え,本件事故態様及び無免許運転その他被告Y1の行動の悪質性に照らすと,本件事故と相当因果関係を有する原告X2の傷害慰謝料としては144万円(原告保険会社が主張する原告X2の傷害慰謝料は119万円であるが,慰謝料額について弁論主義の適用はないし,原告保険会社のB事件(2)の請求は同原告が支払った保険金額を限度とするからこれを上回る認定をしても処分権主義に反することにはならない。)が,後遺障害慰謝料としては110万円が,それぞれ相当である。」
3.2 不貞慰謝料についても擬制自白は成立する?
①~⑤の裁判例は不貞慰謝料に関する裁判例ではなく、交通事故や名誉毀損などに関する裁判例です。
しかし、「慰謝料とは、物質的損害ではなく精神的損害に対する賠償、いわば内心の痛みを与えられたことへの償いを意味し、その苦痛の程度を彼此比較した上、客観的・数量的に把握することは困難な性質のものである」(最高裁平成6年2月22日第三小法廷判決・民集48巻2号441頁参照)であることは不貞慰謝料と交通事故などの慰謝料とで変わりありません。
そのため、これらの裁判例は不貞慰謝料についても妥当するといえます。
したがって、不貞慰謝料はこれを算定する基礎となる事実関係には自白が成立するものの、法的評価を含む慰謝料額には自白が成立しません。
その結果、被告側が裁判の期日に出頭せず、かつ原告の主張を争う旨を記載した答弁書の提出をせず擬制自白が成立する場合でも、裁判所は原告の請求額と異なる慰謝料額を認定できることとなります。
関連記事:交通事故裁判、相手が無断欠席…こちらの請求は全て通る?「擬制自白」の仕組みと注意点
※本記事では「不貞慰謝料の金額について擬制自白が成立するか」について解説いたしました。
しかし、実際の事案では個別具体的な事情により法的判断や取るべき対応が異なることがあります。
そこで、法律問題についてお悩みの方は、本記事の内容だけで判断せず弁護士の法律相談をご利用いただくことをお勧めします。