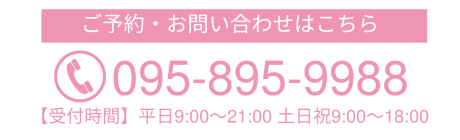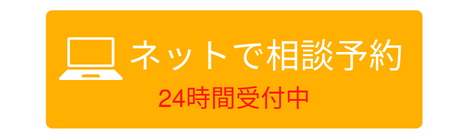Q&A

Q&A
不倫慰謝料の遅延損害金に法定重利は適用される?
Question
いわゆる法定重利について定めた民法第405条は、利息の支払が1年分以上延滞している場合に、債権者が利息を元本に組み入れた上で利息について更に遅延損害金を請求することができる旨を定めています。
では、不倫慰謝料の遅延損害金の支払が1年分以上延滞した場合、法定重利により遅延損害金を元本に組み入れた上、組み入れた遅延損害金について更に遅延損害金を請求することは可能でしょうか。

Answer
これまで、不倫慰謝料請求のような不法行為事案について、民法第405条の適用ないし類推適用により法定重利を認め、損害賠償債務の遅延損害金を元本へ組み入れ、組み入れた遅延損害金について更に遅延損害金を請求することを可能とする裁判例が存在しました。
そのため、不倫開始から1年以上経過している事案において、不倫慰謝料請求の裁判を起こす場合には、あらかじめ延滞中の遅延損害金を損害金元本に組み入れておくというのがベストな対応でした。
しかし、最高裁の令和4年1月18日判決は、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金については、民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることは出来ないと判断しました。
上記の最高裁判例によれば、不倫慰謝料については、遅延損害金の支払が1年分以上延滞したとしても、遅延損害金を元本に組み入れた上で遅延損害金に対する遅延損害金を請求することができないことになります。
不倫慰謝料と法定重利の関係について、より詳しくお知りになりたい方は以下をご覧ください。
1 問題の背景
不倫慰謝料のような不法行為に基づく損害賠償債務は、不法行為時に履行遅滞に陥るとされています(最判昭和37年9月4日民集16巻9号1934号)。
そのため、配偶者の不倫に気づいた時点で不倫が長期間継続している場合や配偶者の不倫に気づいていたものの我慢を続けていた場合という場合には、不倫の慰謝料を請求する際にはすでに1年分以上の遅延損害金が延滞状態にあることが少なくありません。
このような場合、遅延損害金を元本に組み入れた上で遅延損害金について更に遅延損害金を発生させることができるのであれば、複利効果により獲得可能な金額が増える計算となります。
そこで、不倫慰謝料についても、遅延損害金を元本に組み入れるいわゆる法定重利が適用されるのかどうかは重要な問題となります。
2 法定重利とは?
本来、債務者が期限内に利息を支払わない場合には、金銭債務の不履行として利息債務が遅滞に陥った時から遅延損害金が発生するとも考えられます(民法第412条、同第419条)。
しかし、民法第405条は、以下のように規定し、延滞する利息について更に遅延損害金が発生する場合を限定した上で認めています。
民法第405条
「利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。」
民法第405条に基づいて債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることを法定重利と呼んでいます。
なお、民法第405号が元本への組み入れを認める「利息」には、遅延損害金も含まれるとされています(大判昭和17年2月4日民集21巻107頁)。
3 これまでの裁判例
これまでの裁判例としては、不倫慰謝料請求のような不法行為事案について民法第405条の適用ないし類推適用により法定重利を認めるものと、不法行為事案については法定重利を認めないとするものがありました。
そのため、最終的な結論は裁判所次第で変わり得るものの、不倫開始から1年以上経過している事案において、不倫慰謝料請求の裁判を起こす場合の対応としては、あらかじめ延滞中の遅延損害金を損害金元本に組み入れておくというのがベストといえました。
3.1 法定重利を認める裁判例
「不法行為に基づく損害賠償請求権においても、弁済の充当においてもまず遅延損害金に充当されることがあるように、元本とは別に遅延損害金のみを債権者に支払うことは禁じられておらず、不法行為に基づく損害賠償の方法に関する民法七二二条は民法四一七条を引用しているが、これは四〇五条の適用を排除することを意味するものと解することはできず、要は、不法行為に基づく損害賠償請求権について民法四〇五条の適用を排除する理由はないというべきである。」
「原告は,不法行為日から1年を経過した後である平成24年4月24日に被告らに送達された訴状訂正(訴え変更)申立書(平成24年4月23日付け)において,上記元本の組入れを行った旨の主張を行っており,これにより,損害賠償金の支払いの催告及び相当期間を経過をしても支払いがないときは,遅延損害金を元本に組入れる旨の意思表示を行っているものということができる。したがって,平成24年4月24日から本件の損害賠償金の支払いにつき相当期間経過時である同年5月1日の経過をもって,平成23年4月16日から平成24年5月1日までの1年16日間の遅延損害金7万8416円につき元本組入れの効力が生じ,損害賠償金の元本は158万0881円となったというべきであり,被告らは,原告に対し,同金額及びこれに対する翌2日から支払済みまでの遅延損害金を支払うべき義務を負う。」
3.2 法定重利を認めない裁判例
交通事故に関する損害賠償請求事案において、不法行為に基づく損害賠償請求権については民法第405条を類推適用するまでの必要性があるか疑問があるとした上で、債権者による催告額が認容額の約3.6倍であった当該事案においては民法第405条の類推適用の前提を欠く、または債権者が請求額の妥当性を検討する機会を奪っており法定重利の主張を行うことが権利の濫用にあたる、として法定重利を認めなかった。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、催告なしに不法行為の時から遅延損害金が発生する点で債権者保護が図られている上、契約上の債務と異なり履行すべき額が債務者にとって必ずしも明らかとはいえないこと及び原告により催告の基礎となる元本額が認容額の約4.7倍と課題となっていたことを理由に、民法第405条の「利息」には不法行為に基づく損害賠償請求権に関して発生する遅延損害金は含まれないとして法定重利を認めなかった。
4 最高裁の判断
最高裁は、民法第405条を「利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨」の規定とした上で、不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金については、以下の①及び②の点で民法405条の趣旨が妥当せず、法定重利が適用されないと判断しました。
①履行すべき債務の額が定かではなく履行遅滞につき一概に債務者を責めることができない
②何らの催告を要することなく不法行為時から遅延損害金が発生するため遅延損害金の元本への組み入れを認めて債権者保護を図る必要性が乏しい
新株発行が違法であるとして会社の代表取締役に対し損害賠償請求をした事案について、
「民法405条は,いわゆる重利の特約がされていない場合においても,一定の要件の下に,債権者の一方的な意思表示により利息を元本に組み入れることができるものとしている。これは,債務者において著しく利息の支払を延滞しているにもかかわらず,その延滞利息に対して利息を付すことができないとすれば,債権者は,利息を使用することができないため少なからぬ損害を受けることになることから,利息の支払の延滞に対して特に債権者の保護を図る趣旨に出たものと解される。そして,遅延損害金であっても,貸金債務の履行遅滞により生ずるものについては,その性質等に照らし,上記の趣旨が当てはまるということができる(大審院昭和16年(オ)第653号同17年2月4日判決・民集21巻107頁参照)。これに対し,不法行為に基づく損害賠償債務は,貸金債務とは異なり,債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくないから,債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって,一概に債務者を責めることはできない。また,不法行為に基づく損害賠償債務については,何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生すると解されており(最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁参照),上記遅延損害金の元本への組入れを認めてまで債権者の保護を図る必要性も乏しい。そうすると,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金については,民法405条の上記趣旨は妥当しないというべきである。したがって,不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である。」と判断。
5 裁判例を踏まえた実際の対応
最高裁の判例を前提にする限り、不倫慰謝料については、遅延損害金の支払が1年分以上延滞したとしても、遅延損害金を元本に組み入れた上で遅延損害金に対する遅延損害金を請求することができないことになります。
もっとも、不倫慰謝料の遅延損害金の支払が1年分以上遅滞しているという場合、不倫がバレずに長期化していたり、不倫慰謝料の請求に対し請求された側が不誠実な対応を行っていることが少なくないことから、これらの事情を慰謝料の増額要因として主張していくことが考えられます。